ホスピスとは?緩和ケアとの違いやケアの受け方を簡単に解説
2025.04.24 2025.10.23
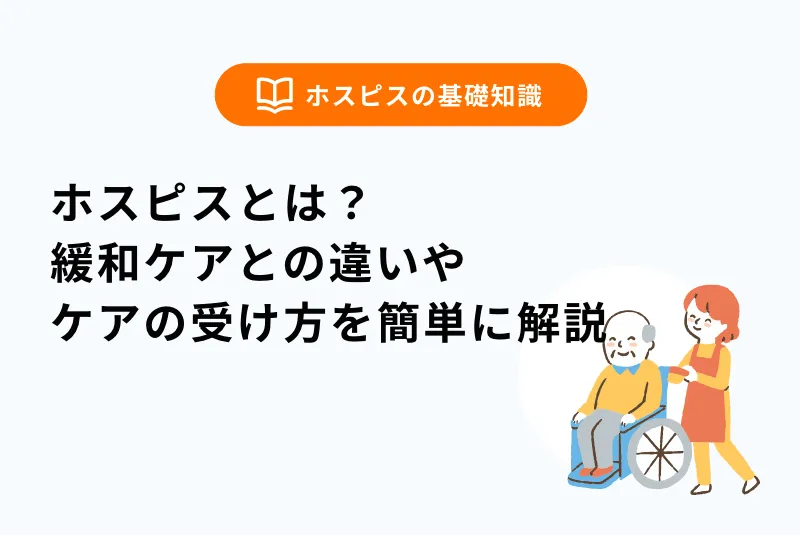
ホスピスとは、終末期の患者さまが心穏やかに過ごせるよう、身体的・精神的な負担を軽減するための医療やケアを提供する施設・サービスです。一般的な病院や介護施設とは異なり、延命を目的とするのではなく、患者さまの尊厳を尊重したケアが中心となります。
本記事では、ホスピスの入居条件や受けられるケア・サービス、ホスピスが受けられる場所などについて解説します。大切な人が安心して最期の時間を迎えられるよう、ホスピスについて一緒に理解を深めてみましょう。
【この記事のポイント】
- ホスピスとは、がん・難病で治療が難しくなった方が自分らしく穏やかに過ごせるよう支援する施設
- ホスピスでは身体的なケア・精神面のケア・社会的なケアが行われる
- ホスピス型住宅に入居するには「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当していなければならない
「ホスピス」とは?
ホスピスとは、がんや難病などで治療が難しくなった終末期の方が、身体的・精神的な負担を和らげながら自分らしく穏やかに過ごせるよう支援する施設です。痛みの管理や不安の軽減に加え、経済的なサポートも含めた多職種の専門家が連携し、患者さまの生活の質(QOL)を維持・向上させることを目指します。
このようなケア、サポートのことを「ホスピスケア」と呼び、ホスピスケアを受けられる介護施設が、一般的にホスピス型住宅と呼ばれます。ホスピス型住宅を含め、ホスピスケアを受けられる場所については後述します。
入居対象者
ホスピス型住宅に入居するためには「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当することが条件です。主にがんの終末期やALS、パーキンソン病などの難病の方、人工呼吸器を使用されている方なども受け入れられます。ただし、認知症が進行している場合は施設ごとに対応が異なりますので事前の確認が必要です。
ホスピスケアの対象者は特定の疾患に限定されず、がん末期やエイズなど、余命が限られた方が対象です。病状の進行により積極的な治療が困難になった際、苦痛の緩和を優先するタイミングで入居を検討します。ホスピスでは身体的な苦痛の軽減だけでなく、精神的な安心や家族のサポートも提供されます。
また、緩和ケア病棟は入院期間の定めがある場合が多く、平均滞在期間は30日未満となります。一方、ホスピス型住宅は入院期間の定めがなく、退院など後の不安なく過ごせることはホスピス型住宅の強みといえます。
なお、ホスピスの利用条件については別記事「ホスピスの利用条件とは?入院までの流れを詳しく解説」と、「ホスピスの入院条件とは?ホスピス型住宅の入居条件や費用も解説」もあわせて参考にしてください。
ホスピスケアと緩和ケアの違い
ホスピスケアと緩和ケアは、どちらも身体的・精神的な負担を和らげることを目的としています。しかし、適用される時期や治療の方針、受けられる場所などに違いがあることを覚えておきましょう。
それぞれの違いについて、以下の表で確認してみてください。
| ホスピスケア | 緩和ケア | |
| ケアを受けられる場所 |
|
|
| 主な対象者 |
|
|
| ケアの方針・目的 |
|
|
緩和ケアは、がんと診断された段階から受けることが推奨されており、必要に応じて治癒を目標とした治療や延命治療と並行して行われることもあるでしょう。一方で、ホスピスケアは余命が限られた方を対象としており、延命治療を行わず、穏やかに過ごすことを優先します。
緩和ケアはがんの治療を行う病院や緩和ケア病棟などで受けられるものです。ホスピスケアは病棟だけでなく、高齢者向け住宅などでも提供されており、長期利用が可能な施設もあることも特徴です。
出典:日本終末期ケア協会「緩和ケア病棟とホスピスは何が違うの?」
ホスピス型住宅・緩和ケア病棟・有料老人ホーム・の違い
ホスピス型住宅と同じように比較される施設として、緩和ケア病棟や有料老人ホームがあげられます。それぞれの違いは、以下のとおりです。
| ホスピス型住宅 | 緩和ケア病棟 | 有料老人ホーム | |
| 目的 |
|
|
|
| ケア内容 |
|
|
|
| 医療体制 |
|
|
|
| 入院・入居期間 |
|
|
|
| 居室 |
|
|
|
| 面会や生活の自由度 |
|
|
|
ホスピス型住宅は、終末期を迎えた方が心身の負担を和らげながら、安心して自分らしく過ごせるようサポートする介護施設です。
緩和ケア病棟は医療の提供に重点を置いており、あくまで入院であるため生活や行動の自由度はホスピス型住宅と比べると低くなります。一方で、有料老人ホームは介護を必要とする高齢者の生活を支援する施設であり、一般的にはホスピスや緩和ケア病棟ほど医療面でのサポートが充実していません。
ホスピスで受けられるケア・サービス
ホスピスで行われるケアには、以下3つがあります。
- 身体的なケア
- 精神面のケア
- 社会的なケア
出典:一般社団法人 全国シルバーライフ保証協会「ホスピスとは、どんな施設?費用や受けられるケアなどを詳しく解説」
身体的ケア
身体的なケアの目的は、病気による苦痛を最小限に抑え、快適な生活を支えることです。主なケアの例には、以下のようなものがあげられます。
- 痛みの緩和
- 呼吸困難を軽減する酸素吸入
- 食事や入浴、排泄のサポート
- マッサージによるリラクゼーション
- 栄養補給のための点滴
- 胃ろうの管理 など
このように、ホスピスでは日常的な生活を問題なく送れるようにするためのケアが行われます。
精神面のケア
病気に伴う不安や孤独感を和らげるための精神的なケアも、ホスピスで受けられるケアの一種です。主なケアの例としては、以下があげられます。
- 看護師や介護スタッフが患者さまとの対話
- 家族や友人との面会
- 季節のイベントやレクリエーション
- カウンセラーやソーシャルワーカーによるカウンセリング など
このように、ホスピスでは患者さまや家族が安心して過ごせる工夫がなされているのが特徴です。
社会的なケア
ホスピスは社会的な側面からの支援も充実しており、医療費や入院費の負担を軽減するためのアドバイスや手続き支援が行われます。主なケアの例は、以下のとおりです。
- 相続や遺言に関する相談
- 介護保険の変更申請
- 住所変更手続きのサポート など
このように、生活保護や公的支援制度についての情報提供を通じ、経済的な不安を軽減する支援を受けられることも特徴です。
ホスピスケアが受けられる場所
ホスピスケアを受けられる施設は複数ありますが、施設としての明確な定義はありません。ケアを受けられる施設としてあげられるのは、主に以下のとおりです。
- 介護施設
- 在宅ホスピス
- 病院
出典:日本ホスピス緩和ケア協会「ホスピス緩和ケアを受けられる場所のご案内」
介護施設
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでは、施設によってホスピスケアが提供されています。上述したように、このようなホスピスケアが提供される介護施設のことを、ホスピス型住宅と呼ぶことがあります。
ホスピスケアが提供されている介護施設には、施設内に介護士や看護師が常勤しているのが特徴です。施設によっては24時間常駐しているケースもあり、24時間の医療ケアを受けられる場合もあります。
ホスピスケアを提供しているサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどは、訪問介護・看護の事務所が併設されているのが一般的です。近隣の医療施設と連携して対応している施設もあるため、介護施設であっても手厚い医療ケアを受けられるでしょう。
在宅ホスピス
ホスピスケアを受ける場所として、自宅もひとつの選択肢としてあげられます。自宅に医師や訪問看護師、訪問介護士などが訪ねて、緩和ケアやホスピスケアを行うのが、在宅ホスピスです。
施設には入らずできるだけ住み慣れた自宅で過ごしたい場合や、移動が難しい方は、在宅ホスピスを選択するケースが多くなっています。ただし、在宅ホスピスを受けるには、家族の協力や主治医との相談が必要不可欠です。
病院
緩和ケア病棟が設置されている病院であれば、入院することでホスピスケアを受けられることがあります。緩和ケア病棟によっては、ホスピスケアが提供されている場合もあるため、入院を考えている場合は病院や担当医に確認してみましょう。
ただし、基本的には緩和ケア病棟は病院のため、あくまでも緩和ケアを基本として延命や根治を目的とした治療が中心であり、すべての緩和ケア病棟でホスピスケアが受けられるわけではありません。
また、病状が良好になったら早めに退院するのが一般的で、平均的に1ヶ月ほどで退院していることを覚えておきましょう。
ホスピスを利用する流れ
ここでは、ホスピスケアを提供している施設や在宅ホスピスを利用する流れを解説していきます。
ホスピス型住宅の場合
ホスピス型住宅でケアを受けるまでの流れは、以下のとおりです。
| 1.主治医やケアマネジャーと相談 | 適切な施設かどうか判断し、介護保険の適用状況を確認する |
| 2.ホスピス型住宅へ問い合わせ | 見学したい施設や比較検討中の施設へ直接問い合わせを行う |
| 3.見学・説明会への参加 | ケア内容や費用について説明を受ける |
| 4.申し込みと面談 | 入居希望を伝え、受け入れ可能か確認する |
| 5.入居決定・手続き | 具体的な入居日を調整し、医療・ケア内容を決定する |
ホスピスに入居すると、一人ひとりの病状や希望に寄り添った医療・生活支援が受けられます。医師や看護師が中心となり、痛みの緩和や栄養管理などのケアを受けられるのが特徴です。
在宅の場合
ホスピスケアは病院や施設だけでなく、自宅でも受けられます。住み慣れた場所で安心して過ごしながら、必要なサポートを受けることが可能です。在宅ホスピスは、一般的に以下の流れで行われます。
| 1. 問い合わせ | 在宅ホスピスを提供している施設・サービスに問い合わせを行う |
| 2. 診断情報提供書の提出 | 案内に従って診断情報提供書などを作成し、患者さまの情報を提供する |
| 3. カウンセリング・面談 | 情報をもとにカウンセリング・面談を行い、在宅ホスピスのケア内容などを詳しく聞く |
| 4. 訪問診療日を決定し在宅ホスピスケア開始 | 診療日を決定し、在宅ホスピスを受ける |
なお、在宅での療養には、訪問介護サービスなどにかかる費用が別途発生することもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
大手ホスピス事業者3社のサービス比較
ホスピスを受ける選択肢として、ホスピス型住宅への入居はとくに多いでしょう。ここでは、大手ホスピス事業者である「医心館」「ReHOPE」「ファミリー・ホスピス」を詳しく紹介します。
| 医心館 | ReHOPE | ファミリー・ホスピス | |
| 設立年度 | 2013年9月 | 2017年3月 | 2011年12月 |
| 施設数 | 全国47都道府県に132施設(2025年8月末現在)
※建設中の施設を除く |
全国に62施設(2025年8月末時点)
※今後オープンする施設を含む |
全国に55施設(2025年8月末現在)
※今後オープンする施設を含む |
| 居室数(総定員数) | 6,753名 | 不明 | 1,300室以上 |
| 居室料金 | 8万5,000円~18万円/月 ※要介護度や居室タイプにより異なる | 約13万円〜(入居金0円、月額費(家賃+管理費)+オプション費用あり。食費は別途 ※各施設やサービスにより異なる | 約13万円~※要介護度や居室タイプにより異なる |
| 問い合わせ先 | 問い合わせフォームかお電話(各医心館の入居相談用の電話番号) | 電話もしくはウェブサイトから
0120-333-527 平日 9:00〜18:00 |
0120-777-160
受付時間:月~日 9:00~22:00 ※年末年始(12/30-1/3)は除く |
なお、自分に合ったホスピス事業者の選び方について詳しく知りたい方は、別記事「ホスピスの選び方とは?選ぶ際のポイントや施設の探し方について解説」をあわせてご確認ください。
医心館
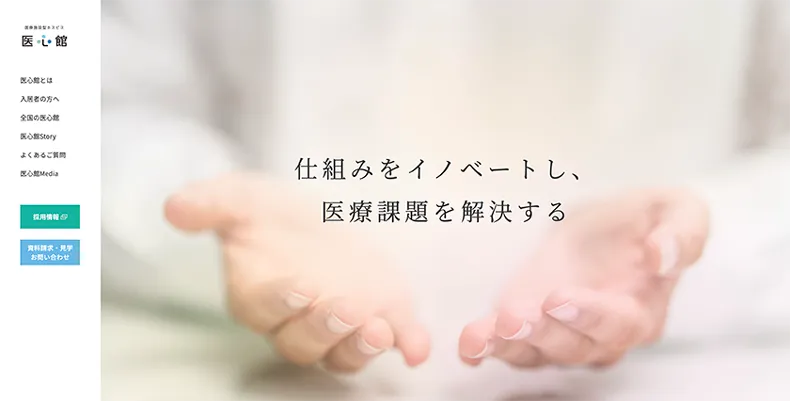
https://ishinkan.amvis.com/
医心館は、医療依存度の高い方が安心して療養できる医療施設型ホスピスです。地域の医師と連携し、高度な看護ケアを提供する「地域医療のプラットフォーム」として機能します。
全室個室(一部施設を除く)でプライバシーを確保しながら、緩和ケアや人工呼吸器管理、栄養補給・輸液療法・ストーマ管理・褥瘡処置などの専門的なケアを受けられるのが特徴です。
ReHOPE

https://cuc-hospice.com/rehope/
ReHOPEは、がん末期や神経難病の方を対象としたホスピス型住宅です。看護師や介護士が常駐していて、24時間365日医療ケアを受けられるため、医療依存度の高い方も安心です。
個室での生活ができ、自分らしい暮らしを尊重しながら、緩和ケア認定看護師による専門的なケアを受けられます。家族との連携を大切にし、安心して過ごせる環境を提供しているのがReHOPEの特徴です。
ファミリー・ホスピス

https://family-hospice.co.jp/
ファミリー・ホスピスは、がんや神経難病の患者さま向けに緩和ケアを提供するホスピス住宅を運営している企業です。24時間365日のサポート体制が整い、専門スタッフによる訪問看護・介護を受けられます。
疼痛管理や人工呼吸器などの医療的ケアに対応し、意思伝達装置の紹介など生活の質向上も支援しています。居室は個室で、外出・外泊も可能です。
公式サイト:ファミリー・ホスピス
ホスピスの費用の目安
ホスピスの利用にかかる費用は、ホスピス型住宅か病院の緩和ケア病棟かによって異なります。ホスピス型住宅のReHOPEを例に、費用相場をみてみましょう。
| ホスピス型住宅(介護施設) | 在宅ホスピス | 病院(緩和ケア病棟) | |
| 月額費用 | 約19.7万円 + 一時入居金 | 約4万円〜7万円 | 約25〜30万円 |
| 費用に含まれるもの |
|
|
|
| 費用に含まれないもの | 施設によってかかるサービス費用 など | 交通費 など | 病院によってかかるサービス費用 など |
ホスピスの医療費については、別記事「ホスピスの医療費は公的制度の対象?変動の要因や利用すべき制度の種類」で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
ホスピスは、終末期の患者が安心して過ごせる環境を提供する選択肢の一つです。病院や介護施設とは異なり、痛みの軽減や精神的なケアを重視し、患者さまと家族の希望に寄り添うことを目的としています。
また、在宅ホスピスも普及し、多様なニーズに応じたケアが可能となっています。本記事を通じて、ホスピスやホスピスケアの基本を理解し、適切な選択ができるようお役立てください。人生の最終段階をより良くするために、最適なケアを選びましょう。
FAQ
ホスピスはどんな施設?
ホスピスは、がんや難病の終末期患者が身体的・精神的な負担を和らげ、自分らしく穏やかに過ごせるよう支援する施設です。痛みの管理や不安の軽減に加え、多職種の専門家が連携し、生活の質(QOL)向上を目指します。
詳しくは記事内「「ホスピス」とは?」をご覧ください。
ホスピスケアと緩和ケアの違いは?
ホスピスケアは余命が限られた患者が対象で、延命治療を行わず穏やかに過ごすことを優先します。一方、緩和ケアはがんと診断された段階から受けられ、延命治療と並行することもあります。
詳しくは記事内「ホスピスケアと緩和ケアの違い」をご覧ください。
ホスピスケアは在宅でも受けられる?
ホスピスケアは病院・施設だけでなく、在宅で受けることも可能です。住み慣れた環境でサポートを受けられます。
在宅ホスピスでも病院や施設と同様に、痛みを和らげるケアや心のケア、社会的な支援を受けられます。
詳しくは記事内「在宅の場合」をご覧ください。
ホスピスのひと月の費用はどのくらい?
ホスピスのひと月にかかる費用は、利用する施設によって異なります。たとえば、ホスピス型住宅の場合の月額費用は、約19.7万円 + 一時入居金です。在宅ホスピスの場合は、月額約4万円〜7万円となっています。
詳しくは記事内「ホスピスの費用の目安」をご覧ください。



