ホスピスの医療費は公的制度の対象?変動の要因や利用すべき制度の種類
2025.05.13 2025.05.13
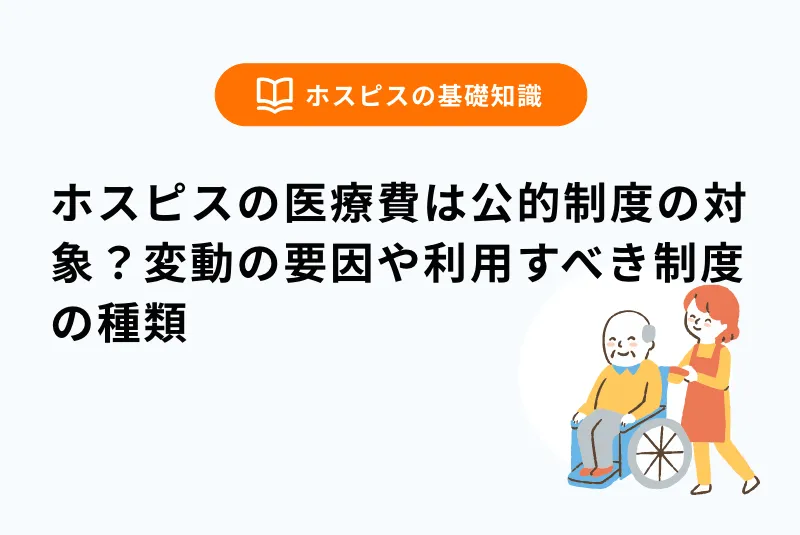
ホスピスでの医療費は公的医療保険の適用を受けられるため、全額自己負担とはなりません。自己負担割合は所得や年齢によって異なり、高額療養費制度を活用することでさらに軽減可能です。
しかし、施設の種類や提供されるケア内容によって費用が大きく変わる点には注意しなければなりません。本記事では、ホスピス医療費の基本的な仕組みや変動要因を解説し、活用すべき公的制度について詳しく紹介します。
【この記事のポイント】
- ホスピスでかかる医療費は公的制度の対象である
- ホスピスでの入院費は1日あたり47,910円の定額制になっている
- 緩和ケア病棟・介護施設など施設の種類でも医療費は変動する
- 高額療養費制度・限度額適用認定証を活用することで医療費の軽減が可能
ホスピスでかかる医療費は公的制度で割引になる?
ホスピスでの治療やケアにかかる費用は公的医療保険の適用となるため、全額を自己負担するわけではありません。保険適用分については、所得や年齢に応じた自己負担割合(1割~3割)が設定されており、高額療養費制度を利用することで一定額以上の負担を抑えることも可能です。
また、低所得者向けの負担軽減措置があり、住民税非課税世帯の場合、自己負担の上限額がさらに低く設定されることがあります。その他、介護保険や特定の助成制度を活用すれば、ホスピスでの生活費や介護サービスの費用負担を軽減できます。
具体的な適用条件や負担額は加入している健康保険の種類や各自治体の制度によって異なるため、事前に確認することが重要です。
そもそもホスピスでかかる医療費ってどれくらい?
ホスピスでの入院費は、厚生労働省により1日あたり47,910円の定額制が適用されています。入院費には医療処置や緩和ケアが含まれ、かつ公的医療保険が適用されます。ただし、自己負担額は年齢や所得に応じて異なることを覚えておきましょう。
69歳以下の場合は自己負担割合は3割となり、1日あたり約14,373円の支払いが発生します。一方、70歳以上は1割または3割負担の対象となり、自己負担額は最大で約4,791円~14,373円程度です。
加えて、入院中の食事代や個室利用による差額ベッド代などは保険適用外となり、別途負担が必要となる点にも注意が必要です。
ホスピスでの医療費は施設の種類でも変動する
ホスピスを利用する際にかかる費用は、どの施設を選ぶかによって大きく異なります。病院の緩和ケア病棟や介護施設でのホスピスケア、自宅での在宅ホスピスなど、それぞれの料金体系や公的支援の適用範囲が異なると理解しておくことが重要です。
緩和ケア病棟
病院内に設置された緩和ケア病棟では医療保険が適用されるため、支払う入院費は厚生労働省の定める定額制の範囲内です。1日あたり47,910円の入院料が設定されており、自己負担額は健康保険の負担割合によって変動します。
69歳以下では3割負担となり、70歳以上は1割または3割の自己負担です。加えて、食事療養費や個室料金などは別途発生するため、全体の費用は病院の設備や個室の利用状況によって変わることを考慮する必要があります。
介護施設
介護施設で提供されるホスピスケアは、施設ごとの料金体系によって費用が変動するのが特徴です。有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの施設では、月額費用に介護サービス料や生活費が含まれています。
医療保険の適用が限定的であるため、施設によっては医療行為が制限されることもあります。ホスピス専門のプランがある介護施設を選ぶことで、医療ケアと日常生活支援のバランスを取ることが可能です。しかし、その分費用が高額になるケースも少なくありません。
在宅ホスピス
自宅でのホスピスケアでは、訪問診療や訪問看護が中心となります。医療費は公的医療保険の適用範囲内で支払われ、介護サービスに関しては介護保険の対象となるため、一定の自己負担で利用可能です。
病院や施設に比べて費用は抑えられる傾向にありますが、家族のサポートが必要になります。そのため、精神的・身体的な負担も考慮することが大切です。
医療費の軽減が可能な公的制度の種類
ホスピスの利用にかかる費用は、公的制度を活用することで抑えられる可能性があります。ここでは、医療費負担の軽減に役立つ「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」について解説します。
高額療養費制度とは
病院での診療や入院による医療費は、公的医療保険によって一部が補助されます。自己負担が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みが「高額療養費制度」です。
高額療養費制度では、1ヶ月(同月内)の自己負担額が所得に応じた限度額を超えた際に、超過分が後から還付されます。所得の区分ごとに定められた自己負担限度額があり、例えば年収が低い世帯ほど負担額は少なくなります。さらに、直近12ヶ月の間に3回以上利用すると、4回目以降の自己負担額が軽減される仕組みが設定されているのも特徴です。
高額療養費制度を利用するには、医療費を支払った後に加入している健康保険組合や市町村の国民健康保険窓口に申請し、所定の手続きを行います。申請の際には医療費の領収書や保険証が必要となるため、適用対象か事前に確認し、計画的に準備することが重要です。
限度額適用認定証とは
高額な医療費がかかる場合、一時的な負担を抑える方法として「限度額適用認定証」があります。限度額適用認定証は、医療機関での窓口支払いを自己負担限度額までに抑えるための証明書です。
事前に限度額適用認定証申請のうえ病院で提示すると、1ヶ月の支払い額が設定された限度額を超えないよう調整されます。例えば標準的な所得の世帯では、一定の範囲内での支払いにとどまり、超過分を後から払い戻してもらう必要がなくなるのです。
限度額適用認定証の申請手続きは加入している健康保険の窓口で行います。発行までに時間がかかることがあるため、ホスピスの利用が決まったら早めに準備すると良いでしょう。
まとめ
ホスピスの医療費は公的医療保険の適用範囲内であり、高額療養費制度や限度額適用認定証を利用することで自己負担を抑えられます。施設の種類によって費用は異なり、緩和ケア病棟や介護施設、在宅ホスピスなど選択肢によって支払い額が変動します。
適用される制度を理解し、必要な手続きを早めに行うことが、経済的な負担を最小限にするポイントです。事前に情報を整理し、自身やご家族にとって最適な選択ができるよう準備を進めましょう。
FAQ
ホスピスでの医療費は公的制度の対象になる?
ホスピスでの医療費は、公的制度の対象です。所得や年齢に応じて保険も適用されるので、全額を自己負担することは少ないでしょう。
詳しくは記事内「ホスピスでかかる医療費は公的制度で割引になる?」をご覧ください。
ホスピスでの医療費が変動する要因は?
ホスピスでの医療費は、ケアを受ける施設の種類で変動します。緩和ケア病棟では厚生労働省の定める「1日47,910円」の範囲内であり、介護施設の場合は施設ごとの料金体系で費用が異なります。
詳しくは記事内「ホスピスでの医療費は施設の種類でも変動する」をご覧ください。
医療費を抑えられる公的制度は?
ホスピスにおける医療費を抑えるには、高額療養費制度や限度額適用認定証の利用が推奨されます。
詳しくは記事内「医療費の軽減が可能な公的制度の種類」をご覧ください。



